絵本を読むとき、どのようなところに注目して絵本を選んでいますか?
絵?作者?それとも自分が知っている絵本?読んでみて面白かったから?
理由はいろいろありますね。
我が国で出版されている児童書は約30000冊、その中で絵本だけで7500冊もあります。
絵本にもブームがあり、大人が楽しめる絵本も近年ではたくさん出版されるようになりました。
しかし、そういった絵本も子どもたちに受け入れてもらえず、初版のみで絶版になってしまうものもたくさんあります。
そして、新聞や雑誌の書評が話題性を重視するために新刊を中心として店頭に並ぶため、本来子どもに必ず読んでほしいような絵本はほとんど紹介されなくなってきています。
では、どのようにして数ある絵本の中から子どもに合った絵本を選んであげたらよいのでしょうか?
絵本から得られるもの

安全な絵本を選ぶ 3つのポイント
絵本は内容が絵で描かれていて、物語りなどの文章をつけて読ませるものです。
子ども向けの内容のものが多くありますが、大人が読んでも読み応えのあるものや大人対象の絵本もあることを知っておきましょう。
幼児向きのものは、まだ十分に文字が読めないため、大人が物語を読み聞かせつつ、絵を眺めさせるというものが一般的です。
これによって言葉とイメージ(視覚から得た情景)を関連付けさせ、言葉の意味を学習する一種の家庭教育的な効果も期待されますが、より日常的な場では、単に娯楽という側面が強くあります。
そのため、子どもが観るもの・聴くもの として大人は絵本を選びましょう。
<絵本選びの3つのポイント>
1.聞いている言葉から自然に文体感覚が身に付くような美しい日本語で書かれているもの。
2.見ている絵から自然に美的感覚が身に付くようなデッサンのきいた絵で描かれているもの。
3.子どもの発達段階にあった絵本。
子どもの心の成長によって、子どもが楽しめるものや興味を引くものは変わっていきます。
「これがおすすめです!!」
といわれても話の内容が難しかったり、子どもが楽しめないものでは意味がありません。
年齢によって絵本を選ぶというのはそういったことが考えられるからです。
🔶大人向け絵本🔶
 |
価格:1,512円 |
![]()
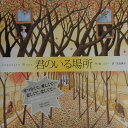 |
価格:1,404円 |
![]() 今は大人向けの絵本も多く出ています。
今は大人向けの絵本も多く出ています。
自分の心に響く絵本を探してみるのもおもしろいですよ。
【年齢別】絵本の選び方
絵本を選ぶ時のポイントは先ほどの3つのポイントを押さえて選ぶことをお勧めします。
そして、それとともに知っておいてほしいことは子どもの発達過程です。
どんなに良い絵本でも、子どもの成長にあっていなければ、いくら読んでも子どもは楽しめず、そっぽを向いてしまうでしょう。
言葉を聞いている0~1歳、言葉をまねて発語をするようになる2歳、話すことが楽しくなる3歳・・・こういった子どもの発達を知ることで、今この子にはどんな言葉を使ったお話がいいのかな?と目を向ける絵本も変わってくるでしょう。
3歳の言葉の発達~言葉で対話を深めていく3歳児
思いを言葉にして伝える力が育ち始めるころ。
目でとらえたことを「ことば」というツールを使って表現する力の育ちは3歳になると飛躍的に充実してきます。
その思いを何とか相手に伝え、相手からも答えを期待する「ことばのキャッチボール」が育っていきます。
しかし、まだ物事をイメージして言葉に変えていく力は十分ではないので、思い浮かべて言葉にするには時間がかかります。
「それでね、あのね、」などの接続詞を使ってコミュニケーションをしようとするのが3歳児の言葉の発達の特徴です。
何度か読んでいる絵本を、ちょっと読み間違いすると、「○○だよ」と指摘を受けることがあります。
耳は一言一句聞き漏らすまいと集中しているのを感じます。
そして、日常的に聞いたことのない言葉や、ちょっとむずかしい言葉、おもしろい言葉などに出会うと、とても敏感に反応し始めます。
言葉をコミュニケーションの道具として使えるようになった3歳児は、周りの大人や友だちと対話をしながらものを考える力が育っていきます。
そして、自分の知らないこと、不思議なことに関心が強まり、「なぜ?」「どうして?」などの問いかけをしながら、知ることの喜びを積み重ねていきます。
読んでもらった絵本をきっかけに、思ったこと、感じたこと、知っていることをしゃべりながら対話を深めていくのです。
この年頃の子どもは、いろいろな物に興味をもつ多感な時期です。
また、多感なゆえに刺激の強い物に興味を持ち楽しみます。
しかしながら刺激の強い物(TVや、光を放つおもちゃなど)を与えすぎてしまうと、子どもの情緒は不安定になってしまいます。
落ち着いた気持ちで一日を過ごすためにも絵本を読むといいでしょう。
夜、寝る前に絵本を読むことを習慣にするとリズムがつくられ、子どもは安定します。
4歳の言葉の発達~言葉でものを考え始める4歳児
言葉を使って目に見えないものを見る力の育つころ。
4歳児になると、話し言葉の完成期に入り、日常会話に困らないだけの1500~2000語ほどの語彙量を獲得するといわれています。
語彙量の増加とともに表現の世界が深まり、気持ちや夢、体験したことのないことなど、目に見えないものも、言葉を使ってイメージする力が育ち始め、その思いを言葉にして相手に伝えようとします。
このように4歳の時期は言葉をものを考える力に変えていく思考機能がもっとも育つ頃といわれています。
考える力の育ちの中で、自分の知らない世界に向かって、想像の翼を大きく広げ始める4歳児は、絵本の世界を行ったり来たりしながら、楽しむ力が育ってくるのです。
4歳児の言葉の発達の特徴の一つとして「内言」があります。
大人は何かを考えたり、自己に言い聞かせたりするとき、頭の中で言語を使いながらも表面的には口に出さずに黙っています。
この頭の中で使っている言葉を「内言」といいます。
「内言」の未発達な幼児は自己に語ると場合も考えていることをすべて口に出し、「外言」を使います。
幼児期後半になると、思考・認識の手段としての言語機能が確立し、さらに行動をコントロールする手段としての機能も発展していきます。
その過程で「外言」と「内言」の中間に位置するつぶやき語が多くなります。
読み聞かせの中でも、絵本からのメッセージを受けて4歳児らしいつぶやきが頻繁にみられるようになります。
ファンタジー絵本や昔話など、いろいろなジャンルの絵本に出会いながら言葉が育っていくのだと思います。
このころになると、子どもの好みもはっきりしてきて、絵本選びが少し難しくなるころです。
また、この時期の子どもたち向けには知育・早期教育を含め、数多くの絵本が出版されていて
「どの絵本を選んだらいいかわからない」
という声が多く聞かれる年齢でもあります。
しかし、子どもに絵本を選ばせることだけはやめましょう。
基本は「ものがたり絵本」を中心に大人が選んであげることが大切です。
お父さん、お母さんが選んだ絵本は子どもを安心させるのです。
5歳の言葉の発達~考えたことを言葉にしていく5歳児
言葉によって自制する力が育つころ。
「~だけど~する」という、行為の自己調整機能の育ちが顕著になり、その中で自我を発見していくのが5歳児の特徴です。
自我の発達は他者を認めることをおたらし、相手の立場や気持ちがわかる力を育てます。
いろいろな物事を、見る、聞く、触れる、嗅ぐ、味わうなど五感でとらえ、そのことを自分の思ったことや考えたこととして言葉に変えて表現していくようになります。
そして、その心の中で考え、相手に伝えたいことを言葉にしていく内言が豊かに育ち始めるのが5歳児なのです。
言葉が人間の持つ最高の象徴機能であることを理解し始めた5歳児は言葉に対する関心がとても強くなってきます。
「しりとり」や「さかさことば」「なかぬきことば」や「はやくちことば」などをして楽しんだりするようになります。
この歳になると、そろそろ文字を覚えて自分で字が読める子どもがでてきます。
しかし、自分で読み始めると途端に文字に集中してしまい物語を楽しむことができなくなってしまいます。
絵本は言葉を耳から聞いて、絵を読んで、創造の世界を楽しむもの。
「文字を読む楽しみ」と「絵本を読む楽しみ」は全く別の事だと言えるでしょう。
文字は言葉を記号化したものです。
文字の獲得の前に、その子の中にたくさんの「言葉」が必要です。
読み書きの前に、「聴く」「話す」ができる事が大切なのです。
まだ?と思われるかもしれませんが、小学校2年生くらいまでの読書は自分で読むのではなく読んであげるのがよいでしょう。
「読み聞かせが大事」なのはなぜ?
自分で読めるようになったら読み聞かせをしなくてもいいのでは?と思うかもしれませんが、文字を読むということは子どもにとっては大仕事。
小学校になってからようやくひらがなを習い、一文字ずつ読めるようになります。
それを「字が読めるから」と言って読むことをやめてしまっては子どもの楽しみを奪ってしまいます。
そもそも子どもは「お話」が大好きです。
わが子たちの通うシュタイナー学園ではどの学年でも必ずお話を聴く時間があります。
自分で読書をする時間ではなく お話を聴く時間です。
お話を聴くということは
1.人の話を聴く力と、ものを見る眼が育ちます
2.子どもの心が豊かになります(ファンタジーの世界)
3.子どもの言葉が豊かになります(言葉の獲得)
そして、家庭での読み聞かせは 親子の豊かな心のふれあいができます。
子どもを確実に本嫌いにしてしまう原因は
「早くから文字を教える」
「自分で読ませる」
「読み終えたら必ず感想を聞く」
だそうです。
反対に本好きな子どもに育てるには「早くから文字を教えない」
なぜなら、文字は言葉を記号にしたものにすぎないからです。
まず必要なのは「言葉の獲得」です。
そのためには
「美しいことば」
「心のこもった言葉」
を耳からたくさん聞くことが大事です。
そして「自分で読むのではなく、読んでもらう」言葉を耳から聴くことが大事です。
早くに文字を覚えて本を読んでいる子は、文字を読んでいるだけで物語を読んではいません。
「ことば」をもとに、イメージを描いてその世界を体験し楽しむことが読書です。
そして、「読んだら読みっぱなし、感想をきかない!」
読み終えた子どもの心は感動でいっぱいです。心からの感動を大切にしましょう。
子どもはどんなに不機嫌な時も、絵本を読んであげるとあっという間に絵本の世界に引き込まれます。
絵と文の総合芸術よ呼ばれる絵本の世界から、子どもたちはたくさんのイメージの世界を受け止め、言葉の力と心を育てていきます。
お話の時間は子どもにとっても、大人にとっても至福の時間となり、お互いの信頼関係を作り出します。
絵本は子どもの心の育ちの源になっているのでしょう。
子どもに絵本は必要なの?
世界で最初の絵本は18世紀イギリスで生まれました。
絵本はことばと絵の関係を効果的に機能させ、読者の理解を広く豊かにするため様々な手法が用いられるようになりました。
20世紀が進むにつれて、絵本はことばと絵の関係が明確でわかりやすい作品は少なくなり、読者の理解力を試され、自分で解釈するように求められる曖昧な読後感を残す作品が増えていきました。
こういったことから、子どもにとって絵本は本当に必要であるとは言えないかもしれません。
しかし、テレビやインターネットの普及によってコミュニケーションが不足している今の時代、絵本は親子の絆を結ぶ大切なものとなっているでしょう。
![]()
スポンサーリンク



コメント