子どものころは、かごめかごめ、あぶくたった、などごく限られたわらべうたで遊んだ記憶しかありません。わらべうたを知ると、子どもと一緒に口ずさんだり、共通の楽しみが増えます。子どもとのコミュニケーションのむずかしさが叫ばれるいまだからこそ、わらべうたは親子関係をより自然に築くよい方法かもしれません。ここでは、コダーイの考えをベースにしたわらべうたの本を中心におすすめの本を紹介します。
『幼稚園・保育園のわらべうたあそび』
コダーイ・メソッドに造詣の深い著者による、春、夏、秋、冬向けの幼児のためのわらべうた集です。季節感のあるわらべうたあそびを体験してみてはいかがでしょうか。まつりやなわとび、手・指あそびなど30を紹介しています。
幼稚園・保育園で子どもたちが歌をうたわない日は一日もありません。お部屋で、園庭で、お友達と一緒に、1人で・・・子どもはよく歌います。いろいろな音楽活動の中で一番ひんぱんに行われる活動だからこそ、保育者は「歌う」ということにもっと教育的配慮をはらわなければならないと思います。この本では、わらべうたを教育的にとらえ、わらべうたのメリットについて詳しく書かれています。わらべうたを子どもたちと歌う時の指導法などものっているので、幼稚園・保育園の先生は覚えておくと、あそびのバリエーションがふえるのでおすすめです。季節によってわらべうたを振り分けられているので、季節を感じるあそびを楽しめるところがいいです。
幼稚園・保育園のわらべうたあそび(春夏) [ 畑玲子 ]
幼稚園・保育園のわらべうたあそび 秋冬 / 畑玲子 【本】
畑怜子、知念直美、大橋三代子/著 明治図書出版/刊
『コダーイ・システムとは何か』
コダーイの理論をハンガリー国内の保育園で実践してきたカタリンさん他による、コダーイ・システムの入門書。ハンガリーの音楽教育の全体像がわかります。ハンドサインも図入りで紹介されています。
F・カタリン、S・エルジェーベト/共著
羽仁協子、谷本一之、中川弘一郎/共訳 全音楽譜出版社/刊
日本語版の初版は1975年と、実に43年前のものですが、その内容は色あせず、むしろ音楽科教育に困惑気味な現代にとって、参考になるのではないでしょうか。
2)こどもの音楽的活動の第一歩は、うたうこと
うたうことと民謡の役割、年齢別の編成、
音楽的諸要素の教授法(1 形式、2 和声、3 移調、4 書き取り〔聴音〕)、
器楽教育へのコダーイ・メソードの適用、結び
小学校以上の音楽科に携わる先生はもちろん、特に幼稚園教諭・保育士の先生に読んで頂きたい一冊です!
【中古】 コダーイ・システムとは何か ハンガリー音楽教育の理論と実践 / フォライ カタリン, セーニ エルジェーベト, 羽仁 協子 / 全 [ペーパーバック]【メール便送料無料】【あす楽対応】
『お母さんとあそぼう わらべうた』
ハンガリーでF・カタリンさんにも師事した著者によるわらべうたが29曲収録されたCD。歌声で聴いて楽しめ、わらべうたのあそび方についてのアドバイスも入っています。

わらべうたの本やCDは、どこにでも沢山出ていますが、本当に良いCDは、そのほとんどが絶版状態にあります。このCDは、知念先生の穏やかで優しい歌声でわらべうたが収録されています。書籍だけでは伝わらない事がCDを聴く事で解決することができます。わらべ歌と一緒に遊び方も教えてくれる、こういうCDはなかなか無いので、本当に貴重です。親子で楽しく遊べて、子どもも喜びます。沢山の保育関係者の方に聴いて欲しい、そして、現場で是非活かして欲しいわらべうたです。
『お母さんとあそぼう わらべうた CD/NO.2』
知念直美/著 明治図書出版/刊
『ハンガリー音楽の魅力』
|
|
『ハンガリー音楽の魅力―リスト・バルトーク・コダーイ (ユーラシア選書)』
横井雅子/著 東洋書店/刊
19世紀以降のハンガリー音楽史を俯瞰する一冊です。大作曲家たちを生んだハンガリーというお国柄が伝わってきます。伝統音楽に可能性を求めたコダーイらの人間性、時代背景も立体的に読めておもしろいです。予備知識がないと少々難しいかもしれませんが、音楽に興味のある人はぜひ読んでみて下さい。ジプシーの音楽の成り立ちがわかりやすくかかれています。ハンガリー音楽を築き上げた人物たちの音楽に対する思いが伝わります。
リストはハンガリー人だったのか―リストと“祖国”のかかわり
リストを招いたハンガリー音楽界 ほか)
2 バルトーク―伝統音楽に新しさを求めた音楽家(バルトークの生涯(一八八一‐一九四五)
伝統音楽との出会い
伝統音楽を研究するということ ほか)
3 コダーイ―人間の声のもつ可能性を信じて(コダーイの生涯(一八八二‐一九六七)
伝統との出会い―人びとの生活の中に残る伝承を求めて
声に秘められた可能性をさぐる ほか)
『わらべうたであそぼう 乳児のあそび』
わらべうたあそびを紹介する書籍の中でも定番のシリーズです。あかちゃんとあそべるわらべうたや語感をたのしむ語呂合わせなども詳しく紹介しています。あかちゃんとのコミュニケーションにぜひどうぞ。
今の子どもたちは小さい時から現代語、それもむしろテレビ語の中にほうりこまれています。大人は日本語を良くも悪しくも話しているかもしれません。しかしそれは、伝承が大切にされなくなってから久しい、明治以後の日本の文化の特殊な“発展”の中で、母語としての深み、味、愛着とは遠くかけはなれていることに多くの人が日常気付かずにいます。この本ではとなえ文句やリズム感のある赤ちゃんがきいて楽しめるものが満載です。0~2歳の子ども向けの内容になっているので、バリエーションも豊富です。乳幼児期は言葉を覚える大切な時期。このときに、わらべうたで日本語の面白さを伝えてみてはいかがでしょう。
【中古】わらべうたであそぼう 乳児のあそび・うた・ごろあわせ 新訂/明治図書出版/コダ-イ芸術教育研究所(単行本)
コーダイ芸術教育研究所/著 明治図書出版/刊
『わらべうたであそぼう 年少編』
子どもが自分でうたいはじめる時期にぴったりの手あそびや歩きながらたのしめるわらべうたを紹介しています。歌いたい年頃の年少さん向けの実用書です。上の年齢でも結構うたはかぶりますが、それぞれの年齢に適した遊びがそれぞれの本で紹介されているので、乳児編をマスターしてから読むとレベルアップした感じが楽しめます。同シリーズには、ほかに年長、年中編もあります。幼稚園、保育園の先生は見ておきたい一冊です。
乳児のわらべうたと大きく本質的に異なる点は、今まで乳児では子ども自身はうたわない、大人のうたをきく、楽しむ、大人のまねごとで参加する、だけであったのがこれからは、自分たち自身がうたい、動いて鼓動を感じたり、あらわしたりすることです。わらべうたあそびではグループになって遊ぶことがありますが、この本では年齢に合ったあそび方ていねいに書かれており、年間計画の立て方も書かれています。保育指導をするときにとても役に立つ一冊です。
【中古】わらべうたであそぼう 年少編 新訂/明治図書出版/コダ-イ芸術教育研究所(単行本)
『新訂 わらべうたであそぼう 年少編・付文学あそび』
コダーイ芸術教育研究所/著 明治図書出版/刊
まとめ
いかがでしたか。わらべうたの本は数多く出ていますが、コダーイの音楽教育に基づいたわらべうたの本は、わらべうたとはどのような効果があるのか、どのような役割があるのか・・・といった教育的な部分もみられるのが魅力的です。幼稚園や保育園で働く方はもちろん、家庭でも親子であそぶときにも活用してみるのにおすすめです。
≪当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。≫
スポンサーリンク
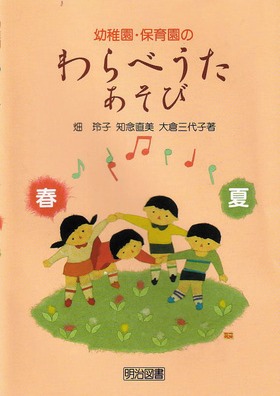



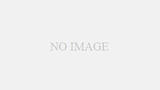
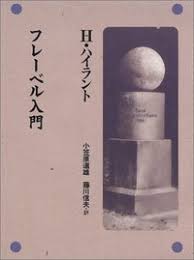

コメント